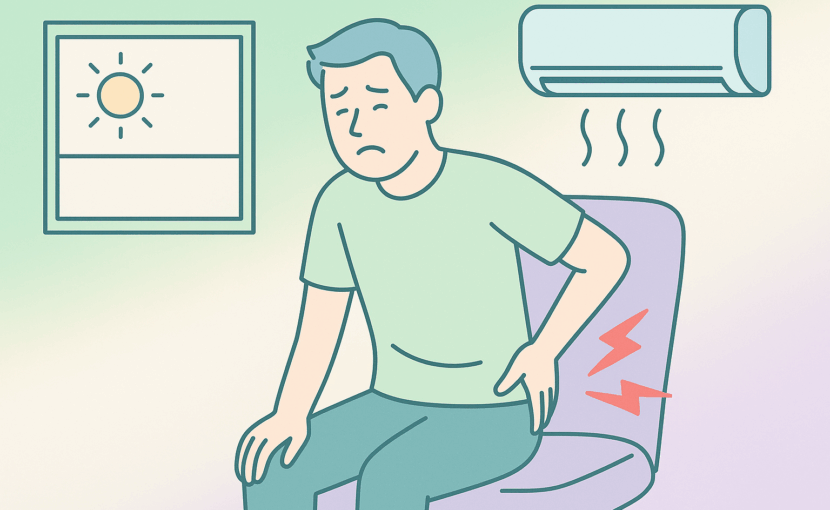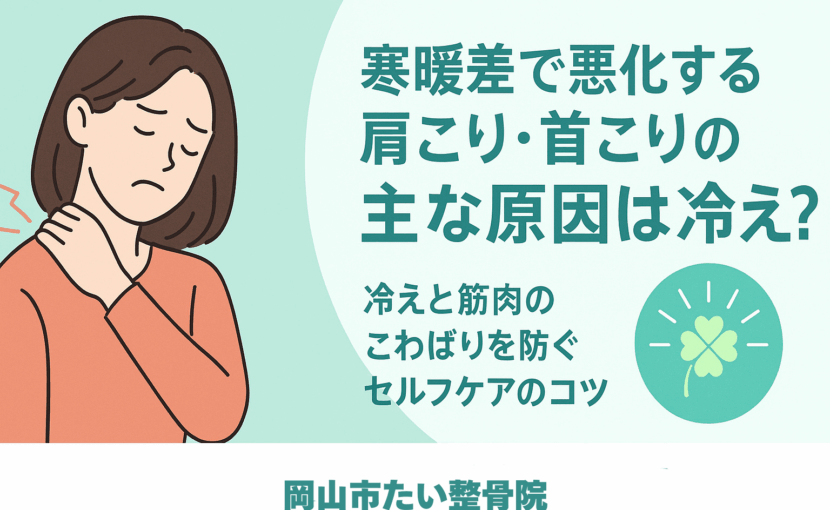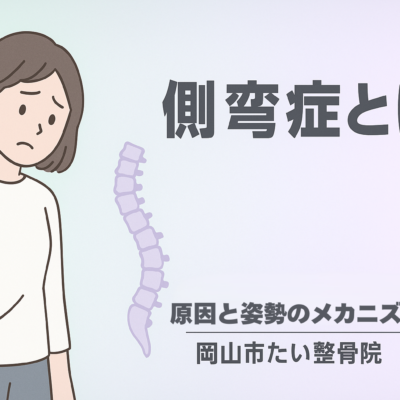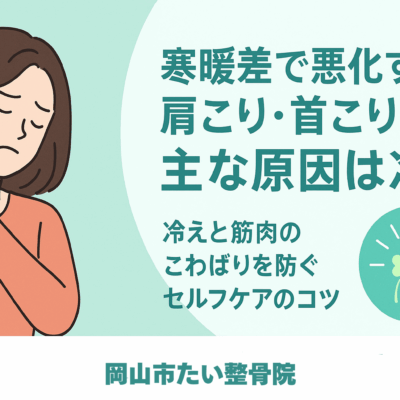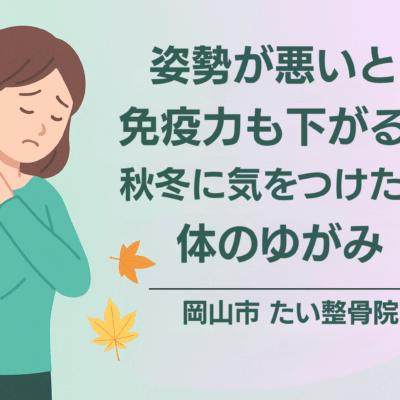「昔から肩こりがひどくて…」
「同じ仕事をしているのに自分だけこる」
「マッサージに行ってもすぐ戻ってしまう」
―そんなお悩みはありませんか?
肩こりは首から肩・背中にかけての筋肉が緊張し、血流が悪くなることで起こります。
頭痛や集中力の低下、眠りの質の低下など、日常生活のパフォーマンスにも大きな影響を与えます。
この記事では「肩こりの仕組み」「原因」「今日からできるセルフケア」「当院での施術方針」を解説します。
肩こりとは?
まずは肩こりがどのような状態なのかを整理しておきましょう。
症状の全体像を知ることで、対策を立てやすくなります。
肩こりは首から肩・背中の筋肉が緊張して血流が低下し、重だるさや張り、痛みを感じる状態です。
ひどくなると頭痛やめまい、吐き気、腕のしびれを伴うこともあります。
ただし、発熱を伴う強い痛み、夜間に目が覚めるほどの激痛、手のしびれや握力低下、胸の痛みや息苦しさがある場合は別の病気が隠れている可能性があるため、まずは医療機関を受診しましょう。
💡 肩こりの概要が分かったところで、次はなぜそのような状態が起こるのか「原因」に目を向けていきましょう。
肩こりの主な原因

肩こりの正体は一つの原因だけではありません。
日常生活の中に潜むさまざまな要因が積み重なって起こることが多いのです。
ここからは、代表的な原因をひとつずつ見ていきましょう。
疲労やストレス
長時間のデスクワークや同じ姿勢の持続、睡眠不足、精神的ストレスは、自律神経のバランスを乱し、首や肩の筋肉を常に緊張させます。
呼吸が浅くなり血流が滞ることで疲労が蓄積し、肩こりが慢性化しやすくなります。
姿勢の崩れ(猫背・ストレートネック)
頭の重さは約4〜6kg。頭が前に出るほど首肩への負荷は増大します。
猫背やスマホ首(ストレートネック)は僧帽筋・肩甲挙筋に持続的な張りを生み、肩甲骨の動きが固くなることでコリが取れにくくなります。
目の酷使・噛みしめ癖
PC作業やスマホでの近見作業が続くと、目の周囲と首肩の筋肉が連動して緊張します。
また歯の食いしばりや就寝中の歯ぎしりは、側頭部〜首肩の筋肉を硬直させ、朝から肩こりを感じやすくします。
体のゆがみ(骨格バランスの乱れ)
骨盤や胸郭の位置が崩れると、首肩の筋肉が姿勢を支えるために過剰に働きます。
左右差や可動域の低下があると一部に負担が集中し、肩こりや背中の張りが長引く原因になります。
冷え・循環不良
冷えは血管を収縮させて筋肉の代謝を落とし、コリを悪化させます。
薄着や冷房、冷たい飲食の取りすぎは首肩の冷えを招き、回復を遅らせる要因となります。
病気が背景にあるケース
頸椎症、椎間板ヘルニア、胸郭出口症候群、五十肩の初期など、疾患が肩こり様の症状を呈することがあります。
しびれ・脱力・発熱・外傷後の痛みは自己判断せず医療機関での検査が必要です。
💡 原因を理解したら、次は「どう対策するか」がポイントです。
ここからは、自宅や日常でできるセルフケア方法をご紹介します。
今日からできる肩こりセルフケア
原因を把握したうえで、次は行動です。
毎日の生活に小さな改善を取り入れるだけでも、肩こりは驚くほど楽になります。
ここからは、今日からできる具体的なケア方法をご紹介します。
姿勢リセットと作業環境の見直し
椅子は座面に深く腰掛け、骨盤を立てて座ることで首肩への負荷を減らせます。
肘は90度、足裏は床にベタ付け、モニター上端が目線の高さ。
60分作業したら2〜3分立ち上がり、肩甲骨を寄せて胸を開く“マイクロブレイク”を習慣化しましょう。
肩甲骨・首のやさしいストレッチ

(A)肩をすくめて5秒→脱力を10回。
(B)肘を横に広げて肩甲骨を背骨に寄せ5秒×10回。
(C)首を左右にゆっくり倒し、突っ張る側の手で耳の上を軽く支える。
痛みの出ない範囲で1回20〜30秒、やさしく行うことがポイントです。
温めケアと入浴
慢性的なコリには温めが有効です。
蒸しタオルを首肩に1回5分、入浴は38〜40℃で10〜15分、呼吸を深くゆっくり行い副交感神経を優位にします。
急に痛めた直後や腫れがある場合は冷却を優先しましょう。
呼吸の質を整える(腹式呼吸4-6)
鼻から4秒吸ってお腹を膨らませ、口から6秒かけて吐き切る。
3〜5分続けると首肩の防御的緊張が緩み、リラックスしやすくなります。
仕事前・就寝前のルーティンにするのがおすすめです。
睡眠・生活リズムの調整
寝具は“高すぎない枕”が基本。仰向けで額と顎が水平、横向きで鼻と胸骨が一直線を目安に。
就寝前のスマホ長時間使用は交感神経を高めるため控えましょう。
生活リズムを整えることが肩こり改善の近道です。
栄養と水分
筋肉の回復にはタンパク質と水分が大切です。
こまめな水分補給を行い、主食・主菜・副菜を意識。
極端な食事制限やカフェインの摂りすぎは緊張を助長する場合があります。
整骨院でのゆがみチェック
自分では分かりにくい左右差や可動域の制限を評価し、必要に応じて骨格・筋膜の調整、運動指導を受けると、セルフケアの効果が持続しやすくなります。
💡 これらの方法を試しても改善しきれない場合や、もっと根本的に体のバランスを整えたい場合は、専門家のサポートが有効です。ここからは当院での施術方法をご紹介します。
たい整骨院の施術方針(岡山市南区西市)
セルフケアだけでは改善しきれない場合、専門家による評価と施術が力になります。
当院では「評価→施術→再評価→ホームケア」のサイクルで、肩こりの根本改善と再発予防を目指します。
・評価:姿勢・可動域・触診・神経学的チェックで負担部位と原因を特定。
・施術:骨格のゆがみを整えるソフトな整体、必要に応じて特殊電気療法で血流と回復を促進。
・運動:肩甲帯の安定化エクササイズや呼吸再学習で“もどり”を防止。
・生活:デスク環境・睡眠・入浴など具体的なセルフケアを個別にお伝えします。
💡 ここまでで、肩こりの仕組み・原因・セルフケア・当院での施術方針を整理できました。
最後にまとめとして、今日からできることと当院からのメッセージをお伝えします。
まとめ
肩こりは「姿勢・生活習慣・ストレス・ゆがみ・冷え」などが絡み合って起こります。
今日からできる小さな習慣(姿勢リセット、やさしいストレッチ、入浴、呼吸、睡眠の調整)を積み重ねることで、多くの方は確かな変化を感じられます。
慢性的に続く、しびれを伴う、強い痛みがある場合は自己判断せず、専門家にご相談ください。
当院からのメッセージ
たい整骨院(岡山市南区西市)は、原因の見極めとやさしい施術、続けられるセルフケアで、あなたの肩こり改善と再発予防を全力でサポートします。
お困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
(監修:柔道整復師 田井 勇次)